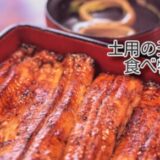2024年の夏至は、6月21日の金曜日ですね。
そもそも、夏至とは何のことかご存じですか?
夏至とは、二十四節気の一つで北半球では「一年で一番昼が長い日」といわれています。
二十四節気とは、古代の中国で作られた1年を24個に分けて季節を表しているものです。
春夏秋冬の4つの季節に分けるのではなく、さらに細かく24に区切って、暦に沿って生活する事で体と心を健やかに保つ事が出来るんですね。

夏至と対になるのが、冬至だね。
春分の日や秋分の日のちょうど間になる日だね。
| 本ページはプロモーションが含まれています。 |
夏至
1年間のうちで一番、昼間が長く、夜が短いのが夏至ですね。これは、北半球の話で、
南半球では、同じ日がもっとも昼の時間が短い日になりますね。

北極圏では、「白夜」になるね!
白夜とは、1日中、太陽が出ている状態だよ!
南極で1日中、太陽が出ていない状態を「極夜」と言うね!
夏至は、陽の気が高まりピークに達します。
夏は、冬に比べて心が活発になりますが、心には負担がかかる季節なのを忘れないようにしましょう。
雨が続く季節で気温も高くなり、体には熱と湿気が溜まりやすくなってしまいます。それにより、湿邪によって胃や腸が弱ります。
内臓の調子が良くないと気分も落ち込み気味になるので、この季節は、汗がかける程度の運動や半身浴をして、しっかりと汗をかくことが大切ですね。
夏至の食べ物【全国】
冬瓜
夏至の食べ物で全国的なのが冬瓜ですね。冬の瓜(うり)と書いて冬瓜(とうがん)です。
冬という字がついていますが、旬は夏です。
ビタミンCやカリウムが豊富に含まれていて、水分補給に適した食材のため夏バテを予防する効果が期待できますね。

【関東】新小麦の焼き餅
関東地方では、新小麦で作った焼き餅が夏至の食べ物とされていますね。
新小麦と同じ量のもち米を混ぜ合わせてついたお餅ですね。
なぜ、新小麦の焼き餅が夏至の食べ物とされているかと言うと、関東地方では米と小麦の二毛作が行われていた事から
神様へのお供え物として田植えの豊作を願って作られていたんです。
焼き餅を食べたらお餅のように粘り強く頑張れそうですね。
【愛知】イチジク田楽
愛知県の尾張地方では、夏至に半分にカットしたイチジクに田楽味噌をつけて食べる風習があるんだそう。
無花果と言えば、不老長寿の果物と呼ばれて薬としても使用されていましたね。
田楽は、「豊作」を願う踊りが由来で、イチジク田楽には、「豊作」と「健康」の願いが込められているそうです。

「花が無い果物」と書いて無花果(いちじく)ですが、
イチジクをカットした中に花があるんだよ!
イチジクは果実の中に花が咲いているんだね。
【三重】みょうが
6月が旬のみょうがですが、三重県では夏至の食べ物とされています。
みょうがには、消化を促進する作用があるため、田植えの後、田植えの労いでお疲れ様の意味を込めて、食欲増進の効果のあるみょうがが食べられるようになったんですね。
【関西】タコ
関西地方では、夏至にタコを食べる風習があります。
この時期は田植えの頃で、「タコの8本の足の様に稲が八方に根を張るように」と豊作祈願でタコが食べられるようになりました。
【京都】水無月
水無月(みなづき)は、見ての通り、白色のういろうの上にあずきを乗せた三角形の和菓子ですね。
この三角形は、氷を見立てており、魔よけの効果があるとされているあずきを乗せて無病息災を祈願したんですね。
夏至の期間、京都の和菓子屋さんには水無月が並びます。

昔は、氷がとても貴重で庶民は食べられなかったんだね。
だから、ういろうを氷に見立てて食べたんだね!
【奈良、和歌山、大阪(河内地方)】半夏生餅、さなぶり餅
半夏生餅と書いて、はんげしょうもちと読みますね。奈良県では、(はげっしょうもち)と読むそうです。
関東地方の新小麦の焼き餅は、焼きますが、半夏生持ちは焼かずに、きな粉をまぶして食べます。
半夏生とは?
そもそも半夏生とは何でしょうか?
半夏生は、夏至から数えて11日目から5日間です。2024年の半夏生は、7月1日(月)です。
古くから「田植えは夏至の後、半夏生の前までに終わらせる」とされています。
半夏生餅は、田植えのねぎらいと神様への感謝の意を込めて食べられていたんですね。
【福井】焼き鯖
福井県の大野市では、半夏生には焼き鯖を食べる風習があります。
農業は重労働ですから、栄養豊富な焼き鯖を食べて疲労回復、夏バテ防止をしようという事から
江戸時代から伝わる風習が今でも残っていますね。
【香川】うどん
香川県では、農作業を手伝ってくれた方々に、その年に収穫した小麦を使ってうどんを作って、感謝のしるしとしてうどんを振る舞うという風習があります。
7月2日は、「うどんの日」と制定されています。
【三重県伊勢市】夏至祭
毎年、夏至の日の早朝、日の出前から始まる行事です。
太陽のエネルギーが最も高いとされる夏至の日に三重県にある夫婦岩の間から昇る朝日を浴びながら禊(みそぎ)が行われます。場所は、伊勢市の二見興玉神社です。
夏至の日の過ごし方
夏至は、太陽が一年で最も高く昇る日ですね。
それは、太陽から地球に注がれるエネルギーが最も強力な日。
この時期は、梅雨なので、夏至の日が太陽が照り付けているという事は少ないかもしれません。
雨が降っていたり、どんより曇っている日である事の方が多いですよね。
でも、夏至の日は、エネルギーに満ちた日です。
「陰」から「陽」の気に転換する時なので、新しいスタートをするのに絶好のチャンスです。
夏至は、何か新しい事を始めるというよりは、気持ち新たに今までの自分を見つめなおす事の方が適しています。
夏至は、早起きをして整理整頓をし、自分の内面と向き合うと良いですね。
2024年6月21日の日の出は4時26分頃です。